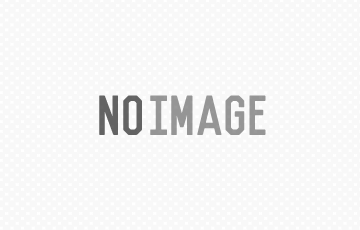お待たせしました。過去問の話題のつづきです。
小6長男、中学受験の国語が大ピンチ!夏前に過去問を始めた理由【前編】
6月後半から過去問を始めた我が家。
週末は必ず4教科の過去問に挑戦してきました。
すると、本人も私も予想していなかった「3つの大きな気づき」があったのです。
これがまた、よかったのやら、悪かったのやら…
親子そろってジェットコースターに乗っている気分です。
では、気づきをご紹介。
気づき1:国語ができないと本人が気づいた(遅い)
まずはこれ。
本人が本当に国語ができないと気づいたこと。
……おっそ!
それまで本人は、塾の宿題で漢字・語句・文法を「まあやってるし~」くらいに思っていました。
親が「それ入試に出るよ!」と何十回言っても響かず。
でも過去問を解いた瞬間に、
「あかーーん!語句も文法も出るやないかーい!全然できひーん!」
と衝撃を受けていました。
やっぱり百聞は一見にしかず。
過去問こそ最強のカウンセラーです。
ビシバシいってやってください。
ということで、これは夏休み前に気が付いて本当に良かったです。
完全ではないですが、語句と文法にも少し力を入れることができました。
気づき2:他の科目を落とせないことに気づいた
国語が崩壊していると、
残りの3科目で勝負せざるを得ない。
ところが長男が受ける学校の理科・社会は配点が低いので、算数を取り切ってもジリ貧になるのです。
本人もその現実を突きつけられて、
「算数、理科も社会は1点たりとも落とせない!」と覚醒。
今まで「まあ、7割くらいでいいか」と甘く見ていたのに、
急に「1点でも多く!」みたいな空気になってきました。
過去問をやり直すうちに、算数・理科・社会も以前より粘り強く解くようになり、親としては「これが副産物か…!」と感心しました。
気づき3:過去問は“楽しい練習試合”だった
これまでの勉強は、
筋トレみたいな地味な下積みでした。
特に小5はキツカッタ。
大量の宿題をさばくことを【習慣づける】って大変ですし、本人もこの宿題がどこに効くのか?なんでこんな繰り返ししないといけないのか?意味が分からないんですよ。
でも、過去問はまさに「練習試合」。
相手チーム(=志望校)との本番を想定して、
点数で勝った負けたがはっきりわかる。
「合格最低点に届いたか?届いていないか?」
このドキドキが小学生にはたまらないらしく、解き終わったあとにやたらテンション高いんです。
まるで部活の試合後みたいに「次は勝つ!」とか「これはいけたな!」と鼻息を荒くしていました。
いや~過去問、
面白いです
親も一緒にハラハラジェットコースターを楽しんでいます。
いよいよ夏休みも終了。
夏を終えて…ここからが本番!
8月後半時点で、国語以外はまずまず戦える状態。だと思う。
国語だけが「お前さえなんとかなれば…!」というラスボス感を放っています。
今になって。本人も「もっと早く国語をやっておけば…」とポツリ。
でも、確実に伸びている。
ジリジリと。
こんなにずーーっと低かったのに、よくやってるよ。むしろ。
長男、最近は背も伸びて中学生に間違えられるようになり、
脳みそも大きくなってきたのか?記憶力や語彙力も少しずつ上がってきました。
精神的な成長が勉強に追いついたような感じもしてきました。
まだまだ国語との戦いは続きますが、
親子で「練習試合」を楽しみながら、
ギヤーギャー騒ぎながら、
突き進むつもりです!
ではでは!
頑張れー!のポチに泣きます。最後まで読んでいただき、ありがとうございます。